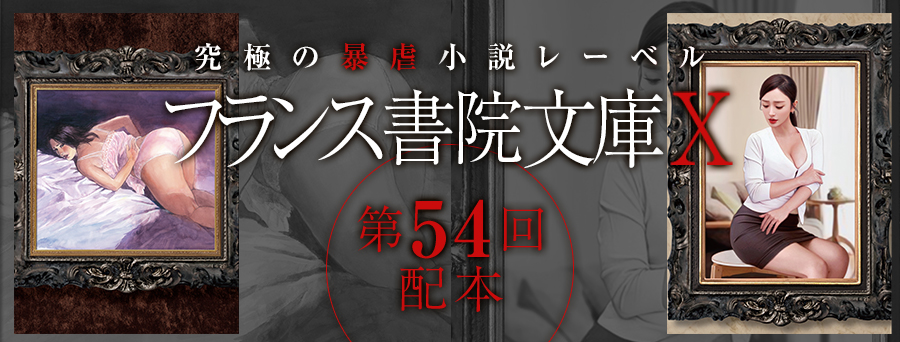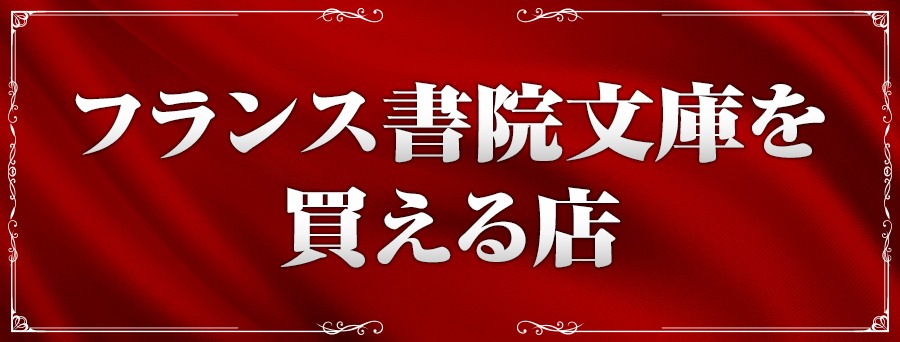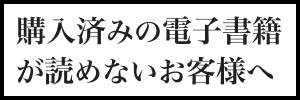メニュー
-
検索
閉じる
- カート 0
- ログイン
新着書籍
04/23(火)更新 04/23
04/10
03/22
02/22
02/09
WEB限定小説
ランキング
新着
電子書籍ランキング
週間ランキング
月間ランキング
ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。ABJマークの詳細、ABJマークを掲示しているサービスの一覧はこちら